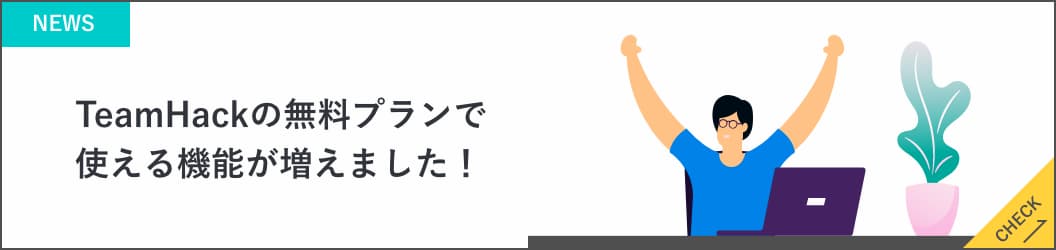企業はビジネスモデル転換を余儀なくされるケースがあります。少し振り返ってみれば、もともとオフィス向けに複合機の製造・販売を手がけてきたメーカーは、ビジネスモデルを転換させています。例えば、富士ゼロックス株式会社は、今や複合機を基軸にした社内の情報インフラ開発まで手がけています。もっと身近な例で言えば、日本を代表する電機メーカーが挙げられるでしょう。もともとは家電量販店で販売される個人向けの電気製品の製造・販売が主軸でした。しかし、いまや企業向けが主になりつつあります。例えば、原発関連を手がける東芝や車関係のエレクトリックシステムを手がけるパナソニックなど。
当然、ビジネスモデルを転換しようとした場合、痛手が伴うケースがあります。いままでの利益の源泉を大きく言ってしまえば「捨ててしまう」ことにもなりかねないからです。
ビジネスモデルの転換にはどのような経緯があり、どんな痛みが伴うのか。そして新たなビジネスモデルに舵を切ったとき、どのようにして成功をつかみとるのか。これらについて事例を踏まえてレポートします。
取り上げるビジネスモデルの転換は私鉄について

今回取り上げるのは大手私鉄のビジネスモデル転換についてです。JR東日本などとは異なり、もともと民間資本であったとされる(厳密には異なるが)企業です。関東であれば東急電鉄、小田急電鉄、東武鉄道など。関西であれば、阪急電鉄、阪神電気鉄道、近畿日本鉄道などが挙げられます。これらの大手私鉄は基本的なビジネスモデルは共通しています。そして、大きく括って見た場合の悩みも同じなのです。いわば業界全体にとって迫られているビジネスモデル転換のニーズが一緒と言えるため取り上げることにします。
私鉄のビジネスモデルを歴史を通じて振り返ってみる
大手私鉄のビジネスモデルは基本的にどの企業も同じと言って差し支えないと考えられます。そしてそれは、阪急電鉄の創業者として知られる小林一三氏が確立したモデルとも言えます。
私鉄はどのようなところから、企業を永続させる利益を得ているのでしょうか? この点の答えとして、実は「鉄道事業」とするのは100点満点ではありません。例えば、東急電鉄を連結ベースで見た場合、鉄道事業から得られる売上・利益は全体の2割程度にとどまります。東急電鉄、と言いながら鉄道事業の収益は柱ではないのです。むしろ、ホテルや商業施設の運営、あるいは沿線での住宅やオフィスビルの開発といった不動産事業。これらの収益のほうが圧倒的に大きいのです。
このような利益構造になっている理由は、先に述べた小林一三モデルが理由に挙げられます。
簡単に言ってしまえば、まず鉄道を敷設します。当然駅もつくります。そうするとそこに人が集まります。今度はその駅を中心にした不動産開発を行い、沿線を商いの場に変えていきます。発展した駅同士の間には人の往来が生じます。その結果、鉄道も儲かるという構造です。
鉄道を敷設し、地域を開発し、また鉄道を敷設する。まるで商いのエリアを「開墾」していくように。これが私鉄のビジネスモデルでした。
バブル崩壊によって決定的に逆回転した私鉄のビジネスモデル
もっとも、私鉄のビジネスモデルは絶対ではありません。むしろ現在では、行き詰まったビジネスモデルになってしまったと言えます。その理由はいくつかあります。
ひとつめは、そもそも鉄道を伸ばすことは今後しづらいということです。すでに確立された路線ネットワークがある現在において、新たに線路を延ばすことは考えづらいのが実情です。関東などではJRからの路線の乗り入れが生じ、実質的に利用者が増加している部分はあります。しかし、鉄道を敷き、あわせて街を作るという旧来のビジネスモデルが実現されるエリアというのはないと言えます。したがって、旧来のビジネスモデルに依拠した場合、成長に限界があるのです。
次に、少子高齢化による鉄道利用者の減少も見過ごせません。簡単に言って、人口が増えれば鉄道の利益も比例して増えます。反対に人口が減れば鉄道の利益も減ります。今後、人口の増加は見込みづらいので、鉄道事業の収益(あるいはその他の事業も含めて)の自然増加は見込みづらいと言えます。
最後に、決定的なきっかけが突きつけられました。それはバブルの崩壊です。より具体的に言えば、右肩上がりの土地価格上昇に歯止めがかかったことが何よりも大きい。旧来のビジネスモデルでは、鉄道を敷設し開発を行うための用地取得を率先して行っていました。そして、これらの事業を進める際に土地価格の上昇は莫大な含み益を生み、さらなる開発のアクセルとなっていったのです。
しかし、いまや土地の価格は市況によって上下する状況。含み益を見込んで用地取得をすると、反対に含み損を抱えてしまうことになります。実際、バブル崩壊後の2000年前後、大手私鉄は取得用地の含み損にあえいでいた時期があります。大手私鉄を合計すると、1兆円を超える含み損があったとさえ言われていたから驚きます。
これらの要因が重なって、旧来のビジネスモデルは逆回転をしはじめたのです。鉄道を敷けない。開発しようにも用地を取得できない。頼みの綱の鉄道も収益はジリ貧になっていくことが目に見えている。八方塞がりだったのです。
ビジネスモデルの転換がどのように図られたか?まずはバブル処理が焦眉の急だった
では、大手私鉄はどのようにビジネスモデルの転換をはかっていったのか。その経緯を追うとき、まず触れなければならないのはバブル処理です。含み損を抱えていた土地。これらについて会計上の損出しをしなければなりません。しかし、時価評価をすれば一気に特別損失を計上する羽目になり、巨大な赤字を生んでしまいます。
そこで、ある種政策的に行われたのが「土地再評価法による不動産価格の再評価」です。これは1度だけ企業が所有する土地価格について時価評価を行い、現在の価格に再評価できるというもの。これを使って、私鉄各社は線路用地の再評価を行ったのです。線路用地は明治、大正期に取得されたものが多く簿価は二束三文の世界。これを現在価格に引き直すと莫大な含み益が発生します。同時にバブル期に取得した土地についても再評価を行い、表面化した損と線路の含み益を相殺しました。結果として、私鉄の財務状況は傷むことなく決算を乗り切ることができたのです。
当時、「これで手持ち資産はすべて時価会計になった」と口を揃えたが、監査法人やアナリスト筋からは「それは建前で、含み損処理でしょ」という声も聞かれる状況でした。しかし、一部の批判はあったものの土地再評価法によって財務面の不安をしのげたのは事実です。新たなビジネスモデルの展開へと駒を進めることができるようになりました。
ビジネスモデルの転換。それは原点回帰、いや「沿線回帰」がスタート地点
では、実際のビジネスモデル転換はどのように進んだのか。その点に話を進めましょう。
結論から言えば、なにか目新しいことをしたわけではありません。「沿線回帰」と「お客様視点の強化」だったのです。
沿線回帰というと、「また沿線で不動産開発をするのか?」と思われる方がいるかもしれません。そうではなく、積極的なリストラを行ったのです。例えば、東急電鉄を例に取れば、沿線で東急ストアというスーパーを運営しています。あるいは、スポーツジムであれば東急スポーツオアシスがあります。要は、沿線に自社ブランドのさまざまな業態を構えていたのです。これらについて、不要なものは撤退し、かわりに他社ブランドで有力なものを誘致しました。簡単に言えば、強いブランドを沿線に連れてくるのです。無論、そもそも人気があったり、しっかり収益が上がっている店舗は残して。こうすることで、沿線の魅力向上を図っていったのでした。沿線、もっと言えば街に人気が出れば鉄道や駅周辺の主要施設を握っているのだから、最終的には自社ブランドを使う機会も増えるという戦略です。
拠点になるターミナル駅への集中投資

次に「攻め」の部分。これも沿線重視で「ターミナル駅への集中投資」を行っていきました。例えば、関西の阪急電鉄を例にあげれば、阪急うめだ駅(厳密には商業エリアである阪急三番街)自体の改修を行い、周辺にある阪急百貨店の改装、阪急メンズ館のオープンなど。ターミナルを中心に商業施設見直しを進めました。近畿日本鉄道であれば、あべのハルカス建設などが良い例です。関東であれば東急電鉄の渋谷駅再開発が挙げられます。ターミナル駅は乗降客数が多いという大きなメリットがあります。そこに歴史的に培った開発事業のノウハウ、自社ブランド意識を反映した展開を導入していき、成功へとつなげていったのです。実際、阪急百貨店を例に取れば、大阪の中心地のひとつである心斎橋周辺の同業他社と比べても賑わいを見せています。
自社ブランドの確立も同時進行で行う
私鉄各社が優れていた点は、地理的に沿線回帰を行ったのと同時に、自社ブランドの再確認を行ったことも大きいと言えます。
経営統合を果たした阪急と阪神を通じて、そのことが確認できます。大阪駅(もしくは梅田駅)には、阪急百貨店と阪神百貨店が間近にありました。統合前は、阪急百貨店はファッションに強く、阪神百貨店はデパ地下に強いという特徴がありました。経営統合後、両方の店舗を改装し、よりブランドイメージを意識した対応を取ったのです。阪急百貨店ではファッションへの強さを強化。メンズの衣料をほとんど扱わず、かわりにレディースの靴、アクセサリー、化粧品といったジャンルを数多く取り揃えるようになりました。また、デパ地下はスイーツに力点を置いています。一方の阪神百貨店は、日常食の取扱いと催事による集客に力を入れて大阪らしい賑わいを重視しています。
これらはちょっとおしゃれな阪急電車沿線、ワイガヤ感のある阪神電車沿線の雰囲気をそのまま反映したものとなっています。
こうして沿線に回帰し、他者から見た自社イメージをグループの事業全体に浸透させていくことで、新しい沿線回帰を成し遂げていっていると言えます。
積極的な原点回帰は、企業にとって決して後退になるものではない
大手私鉄は、結局の所、原点回帰をしただけではある。しかしながら、「原点」を把握していないとそれはできない。また、原点に戻るにしても単純に戻るだけではなく、現有資産を活用して本当にいままでの顧客に答えていたのかを考えなければならない。自社のカルチャーを把握し、自分たちが顧客からどのようなイメージを持たれているかを把握していなければならない。大手私鉄はそれができた、間違っていなかったと言える。そのうえで選択できる戦略を間違いなく選び取る、これが必要なのだ。原点回帰は正しい状況把握と経営判断を持って望めば、けっして企業にとって後退になるものではないのだ。