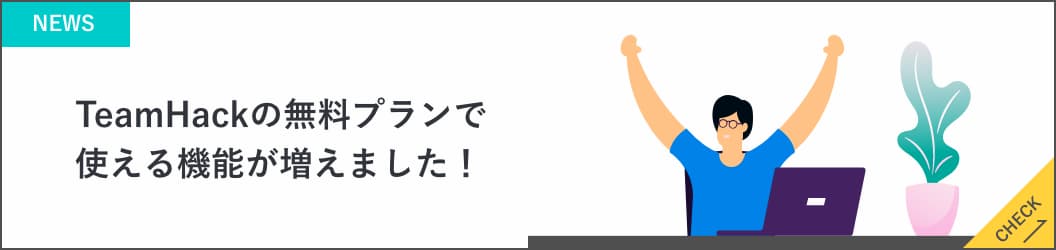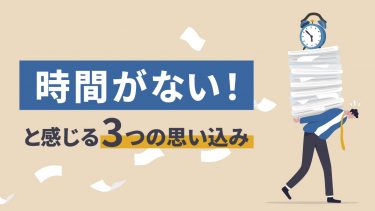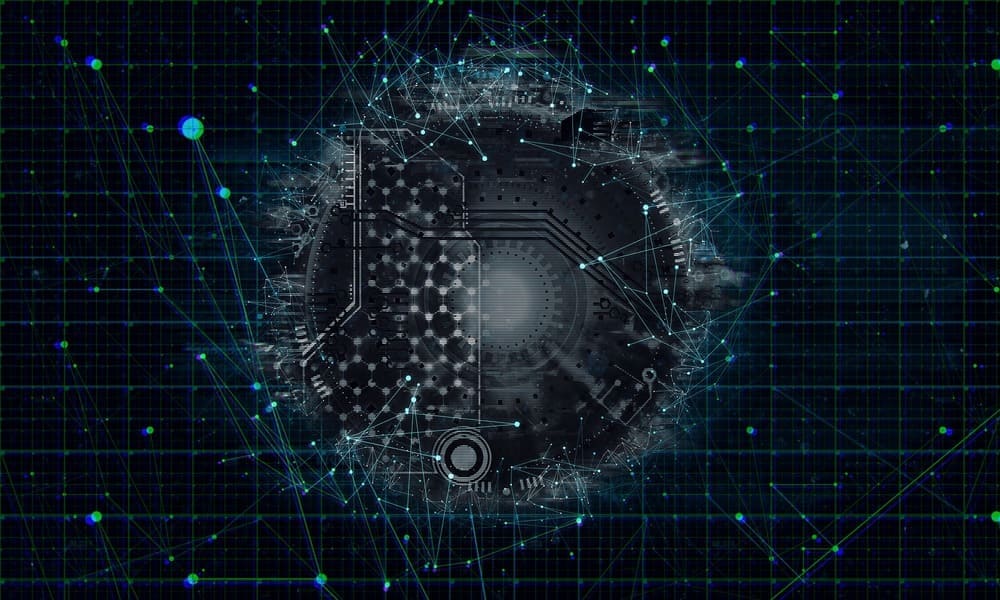給与や待遇決定、キャリア形成など、重要ポイントが複数ある評価面談。評価面談では、今までの業績と行動をもとに評価をし、今後の課題や目標を設定します。
個人や会社が成長するために評価面談は、貴重なチャンスです。
評価をする側、される側それぞれの視点から評価面談の意義について考えてみましょう。
評価面談とは?
評価面談とは、従業員の評価を決めるために、上司(評価者)が部下(被評価者)の話を聞く面談です。四半期や半期に1回、もしくは1年に1回など、一定のサイクルで実施します。一般的に、評価面談は30分〜1時間程度とじっくり時間をかけて行います。
基本的に上司と部下の1対1で行いますが、企業によっては、人事担当者などの複数人を評価者として同席するケースもあるようです。
評価面談の内容を給与や昇進昇格といった人事評価に直接反映する企業は多く、重要性の高い面談といえるでしょう。また、評価面談を人材育成やモチベーション向上につなげる企業もあります。
上司と部下で行う定期的な面談として1on1ミーティングがありますが、1on1ミーティングは「部下と上司のコミュニケーションの場」です。評価面談とは目的や内容、実施頻度が異なるため、混同しないように注意しましょう。
▼関連記事
1on1とは? 必要とされている理由・実施の流れやコツを紹介
評価面談の目的
評価面談には、「人事考課」「人材育成」「従業員の動機形成・モチベーション向上」「マネジメントの課題の発見と改善」といった4つの目的があります。それぞれの目的を具体的にみていきましょう。
人事考課
人事考課とは、業績や貢献度、能力、スキルなどを査定し、その結果を給与面や昇給、賞与などの報酬に反映させる仕組みです。企業で定めた基準に基づき、客観的かつ公平な評価をしなくてはなりません。
組織において、従業員全員の報酬が平等であることはほとんどないでしょう。役職や給与、業務内容など、さまざまな差が生じます。そこで、不平等感のない処遇を決めるために必要となるのが人事考課です。
人事考課と似た言葉に、人事評価があります。二つの言葉に明確な違いはありませんが、人事考課は待遇面を判断するものであるのに対し、人事評価は従業員の能力や勤務態度などを総合的に評価するものとして使用されています。
人材育成
評価面談では、上司の主導のもとで部下の業務の取り組みについて振り返ります。業績や貢献度、スキルを査定し評価することで、おのずと課題や改善点などの要素が浮き彫りとなるでしょう。
何ができていて、何ができていないのかを客観的にみることで、部下は自分の現状を把握でき、何をすべきかが明確となります。自分では気づいていなかった強みや弱みも明確となるでしょう。
会社がどのような評価をしたかを伝えるだけではなく、評価によって明確となった改善点や課題点、これからの業務で期待することを伝えることで、従業員の成長を促すことができます。
従業員の動機形成・モチベーション向上
評価面談は、従業員の動機形成やモチベーションを向上させる絶好の機会でもあります。
目先の業務ばかりに意識が向いていては視野が狭くなり、仕事のやりがいを見失いがちです。評価面談では、今の仕事がどのような意義を生み出しているのかをきちんと伝えることで、部下のモチベーション向上を促しましょう。
仕事の大儀を説明しながら、部下が目指す理想像を聞くのもよいでしょう。現在の業務と理想像を紐づけることができれば、仕事に対して意欲的に取り組む大きな動機形成へとつながります。
マネジメントの課題の発見と改善
部下の処遇を決定する評価面談は、チーム全体の状況や問題点を見直す機会にもなります。
部下の成績が伸び悩む要因のひとつとして、上司のマネジメント方法に課題があることも珍しくありません。業務がスキルに見合っていなかったり、業務量に偏りがあったりなど、正しいマネジメントができていなければ、部下も力を発揮できないでしょう。
業務の割り振りや人材の適材適所など、マネジメント側の課題を発見し、改善することも評価面談の重要な目的です。評価者側のマネジメントを振り返ることで、上司のマネジメント力向上にもつながります。
評価の仕組み
評価面談での評価は、どのような仕組みで成り立っているのでしょう。評価の仕組みを知ることで、被評価者は面談に備えて準備ができます。また、評価をする軸が分かっていると、自己評価もしやすくなるでしょう。
能力評価
業務の中で習得した知識やスキルを評価します。
例えば、デザイナーの評価面談のケースでは、デザインセンスや表現力、PC操作スキルはもちろん、作業の速さや正確さなどが該当します。
また、業種や職種によって異なりますが、コンプライアンスに対する意識や業務の先々を見る視座の高さ、トラブルに適切に対応できるリスクマネジメント能力、メンバーとのコミュニケーションやチームワークなど、さまざまな項目にわたって評価を行います。
難しい案件やスピード感を求められる案件にトライしてスキルアップすると、高い評価につながるでしょう。
情意評価
情意評価は業務に対する意欲や関心、態度に対する評価です。
評価項目の中でも比較的定量化しにくい項目であり、会社のポリシーや人材育成の考え方によって評価項目が変わります。
「被評価者が組織にどの程度貢献しているか」という基準を持って、勤務態度やチームへの影響、業務への責任感、ビジョンや理念に基づいた行動をしているかなど、規律性や協調性の観点で評価します。
情意評価は具体的な成果を示しにくいため、評価面談をすることで評価ができるようになります。目に見えにくい項目を評価することで、メンバーのモチベーションアップも期待できます。
業績評価
業務に対する成果やそのプロセス、業績に基づいて評価するのが業績評価です。主に、目標と期間を決め、期間が終わった後に振り返りを行います。
目標達成率やプロセスの有用性など、客観的な数値を見て評価します。結果が全てなので、定量的で分かりやすい評価項目といえます。
もし目標達成率が低いと評価されないかというと、そうではなく、振り返りの精度や努力したプロセスをもとに、将来性が評価されるケースもあります。
業績評価によって高い評価を得たメンバーは、報酬アップや昇進・昇格につながることも少なくありません。一方、成果や業績を残すことができないメンバーは、評価が下がり、報酬カットや降格になることもあるでしょう。
【評価者向け】評価面談の進め方
では、メンバーと会社の成長を促進する評価面談とは、どのような面談なのでしょう。被評価者の本音を引き出し、モチベーションを高めるような評価面談の進め方について、考えてみましょう。
アイスブレイク
無駄な時間を削減したシンプルなコミュニケーションが好まれる昨今ですが、評価面談におけるアイスブレイクは重要な役割を持っています。
席に座った直後から評価についての話をすると、被評価者が緊張して率直な意見交換ができないかもしれません。場の緊張を和ませるためにも、趣味や家族の話など、敢えて評価とは関係のないカジュアルな話題から面談をスタートさせましょう。
被評価者にとって答えやすい話題をふると、緊張がほぐれて評価面談での会話もはずむはずです。
これは評価者にとっても有効な時間で、この後の評価が伝えやすくなります。互いにリラックスした雰囲気が作れたら、徐々に評価面談の本題に移ります。
被評価者からの自己評価のヒアリング
アイスブレイクの後には、被評価者の自己評価を聞きましょう。面談の前に、自己評価のポイントなどを共有しておくと、スムーズなヒアリングができます。
被評価者による自己評価は、面談の最初に聞いておくことが重要です。先に評価者による評価を伝えてしまうと、被評価者が話を合わせてしまい、本音を聞き出しにくくなってしまいます。
それぞれの評価に相違がある場合も、しっかりヒアリングしておくことで、評価の違いがどこから生まれたのかを面談の場で明確にでき、被評価者に反発的な気持ちを抱かせずにすみます。
自己評価のヒアリングでは、途中で遮ったり否定したりせず、被評価者の話に集中しましょう。話を聞いてくれる評価者でないと、被評価者は本音を話したり評価を素直に受け止めたりできなくなってしまいます。
評価結果のフィードバック
その後、評価者から評価結果をフィードバックします。評価結果をフィードバックする際には、伝える順番に留意しましょう。どんなにアイスブレイクを行っても、評価を伝えられる側にとって、緊張が高まる瞬間です。
ほとんどの場合、ネガティブな評価には気分が沈み、受け入れるのは容易ではありません。必要以上に落ち込ませないために、話の順番を工夫したり、相手に合った表現を用いたりしましょう。
まず、ポジティブな評価を伝えましょう。ネガティブな評価はその後です。
ネガティブな評価の中でも、本人も自己評価で自覚していたネガティブな評価から伝えたほうが、受け入れやすいと考えられています。最後に、本人は自覚していないネガティブな評価を伝えます。
評価を伝える時には、明確な基準を示すことが大切です。なぜそのような評価になったのか、丁寧に説明しましょう。
現状の課題のすり合わせ
双方で認識が異なる評価を中心に、意見のすり合わせを行いながら、被評価者が解決すべき現状の課題を見つけましょう。
課題は評価者が決めて一方的に与えるものではありません。評価者に与えられた課題は、「やらされている」と感じやすく、意欲的に取り組めない場合もあります。
主体性をもって課題に取り組んでもらうためにも、被評価者と対話をして掘り下げることが大切です。本人が気づきを得ることで、課題として受け入れやすくなるでしょう。
今後の目標のすり合わせ
課題が見えたら、解決方針や改善策を考えます。ここですり合わせを行うことで、今後の目標が明確になります。課題をクリアし、よい評価を得るための具体的な目標を決めましょう。
被評価者の今後のキャリアプランやビジョンを聞くと、より適切な目標を設定できます。
課題同様、目標も評価者が与えるものではありません。被評価者が改善案を考えることでモチベーションにつながり、積極的に課題の解決に取り組めるようになります。
また、被評価者自身にすり合わせた結果を取りまとめてもらうと、本人の理解度が分かります。理解のズレや不足がある場合は、認識のすり合わせの時間をとりましょう。
まとめ
最後に、評価面談の内容をまとめます。共有した課題や目標、今後の行動指針を再確認するためにも、部下に話をまとめてもらうよう促しましょう。部下自身が振り返ることで、理解度を深めることができます。
また、評価面談を行った感想を聞いてみるのも良いでしょう。評価者視点とは異なる気づきを得ることができ、今後の評価面談に活かせます。
評価面談がどのような内容であれ、最後はポジティブな言葉をかけて終わることが大切です。活躍を期待している思いや頑張ってくれていることへの感謝の気持ちを伝え、お互いに明るい気持ちで面談を終了するように心掛けましょう。
【評価者向け】評価面談の注意点
評価面談には、以下のような注意すべき点があります。成長を促進するための評価面談によって、評価者や会社に不信感を抱いては意味がありません。被評価者・評価者ともに、よい面談にするために、以下の4つのポイントをおさえておきましょう。
評価内容、何を伝えるかを事前に整理
評価面談に欠かすことができないのが、事前準備です。評価やその根拠が曖昧だったり、面談の進め方に違和感を覚えてしまったりすると、何を伝えても納得できないかもしれません。
被評価者に伝える評価は、あらかじめまとめておきましょう。
まず、評価面談の目的を明確にします。特に評価面談の目的に相違があると、評価も課題も現実味を持ちません。
具体的な評価内容や評価の根拠を伝える際は、被評価者の自己評価とのギャップはないか、どのように伝えれば理解してもらえるかを、事前に整理しましょう。また、話すテーマが多すぎると本質が伝わらない可能性があるので、絞って伝えることを意識します。
また、被評価者から出てきそうな質問や意見も想定し、適切な回答や対処方法をイメージしておくとスムーズです。
静かな個室で行う
評価面談は、静かな個室で行いましょう。他の人には聞かれたくないセンシティブな話題になることもあります。他のスタッフの出入りがある場所や話が漏れるような場所、周囲の視線が気になる場所では、気兼ねのない面談にならず、意見しにくくなってしまいます。
評価者と被評価者が1対1で話せる会議室などを確保し、面談に集中できる環境を用意しましょう。
評価面談は1時間以上の時間を要することもあるので、部屋の予約が必要な場合、余裕を持って確保します。
また、静かな個室での面談によって、被評価者は評価面談の重要性を認識しやすくなります。貴重な機会であることを理解でき、真摯に向き合う面談になるでしょう。
被評価者の話をよく聞く
評価面談は評価を正しく伝え、今後に活かすことを目的としていますが、評価者が一方的にフィードバックするだけでなく、被評価者の話にしっかり耳を傾けて、信頼関係の構築に努めましょう。
自分の意見をしっかり聞いてくれた人の話であれば、評価や課題を素直に受け入れることができ、耳が痛いネガティブな評価を伝えたとしても、相互の関係性を良好に保てるはずです。もし、被評価者の話を聞かないまま評価面談を進めてしまうと、評価を押し付けられたように感じ、モチベーションの低下につながりかねません。
腕を組んだり他のことをしながら話を聞いたりすると、威圧感を与えたり不信感を与えたりします。話を聞く姿勢を整え、顔や目を見る、適度に相槌をうつなどし、話しやすい雰囲気を作りましょう。
また、どんなに質問や訂正をしたい場面があっても、話を遮ることはせず、最後まで聞きましょう。伝えたいことがある場合、全て話し終わるまで待ちます。
ダメ出しだけではなく期待を伝える
互いにポジティブな気持ちで評価面談を終えるためにも、ダメ出しだけでなく期待を伝えましょう。被評価者の強みや伸ばすべきところを意識した面談を心掛けます。
他者からの評価によって、これまで意識していなかった思わぬ強みが見つかることも珍しくありません。被評価者にとってプラスになることは、積極的に伝えてください。評価面談をきっかけに、目標を強く意識した行動が取れるようになるでしょう。
評価面談を行う際には、コーチングが有効です。コーチングとは、相手の話をよく聞き、観察し、質問を繰り返すことで、本人も気付いていない本質的な答えを引き出す手法です。目指すべき目標が明確になり、自発的な行動を促します。
コーチングの手法は「コーチングとは? ティーチングとの違いや使い分け、手法を解説」にまとめています。
面談後のフォローを実施する
評価面接をした後は、そのまま部下を放置するのではなく、フォローすることも大切です。いくら部下の話を丁寧に聞いたとしても、面接後にフォローを実施しなければ、新たな不満やストレスが発生する可能性もあります。
面談で評価した後は、積極的にコミュニケーションの場を設けることが大切です。部下のことを気にかけ、効果的なコミュニケーションを図ることで、部下のモチベーションを保つことができるでしょう。
円滑なコミュニケーションを取れる信頼関係を築くことができれば、風通しのよい職場環境となり、組織全体の生産性向上につながります。
【評価者向け】評価面談をスムーズに進めるための質問テクニック
評価面談は、部下の業務実績に対するフィードバックを行う場でもあり、対話することが重要です。上司が一方的に話すだけでは圧迫感を与えてしまい、部下は本心を言いづらくなってしまうでしょう。
ここでは、評価面談をスムーズに進めるために役立つ、「拡大質問」と「肯定質問」を紹介します。
拡大質問
拡大質問とは、オープンクエスチョンとも呼ばれる質問テクニックです。相手の思考を知りたい時や会話を広げたい時に有効です。「なぜそうなったか」「どうしてその目標を設定したのか」などが、拡大質問にあたります。
反対に、「はい」「いいえ」などの限られた選択肢の中から回答を得る質問を、限定質問またはクローズドクエスチョンと呼びます。限定質問は話が膨らみにくく、連続して続けることで誘導尋問のような圧迫感も与えてしまいます。
部下の話を引き出すためにも、評価面談では拡大質問を活用します。例えば、部下の改善すべき点について話し合う際には「どんな改善方法があるかな?」「そもそもの原因は何だと思う?」などのように、自然に話を広げられる質問をしましょう。
部下にとっても、自分自身の課題をより深く考えるきっかけとなります。「今後何をすべきか」が明確となり、改善にも意欲的に取り組めるようになるでしょう。
肯定質問
肯定質問とは、「ない」という否定形の言葉を含まない質問テクニックです。
部下の業績や勤務態度を指摘する場合、「どうしてできないのか?」「何がわかならないのか?」と聞いてしまうと、否定的な印象となり、部下は萎縮してしまうでしょう。しかし、「どうすればできるようになるかな?」「これに取り組むことにはどんな意味があるかな?」などと肯定的な質問をすることで、ポジティブな印象を与えられます。
否定質問は、言い訳や原因の追究になってしまい、考えや答えを引き出せる可能性は低くなります。ただでさえ緊張感のある評価面談では、なるべく控えたほうがよいでしょう。
一方、肯定質問はできない理由を聞くのではなく、できる方法を聞く質問です。前向きな意欲を与え、行動を促せるため、評価面談では上手く活用したい質問テクニックです。
【被評価者向け】評価面談で評価が上がる人
ここからは、実際にあった評価面談において、「この社員スタッフの評価を上げよう」と感じた行動と特徴を紹介します。
事前に振り返りを行い自己評価をしている
評価面談で評価が上がる人の特徴として、評価面談の前に自ら振り返りを行い、自己評価をしていることが挙げられます。
評価面談は、人事評価に直結するため、緊張して言葉がでづらくなるものです。上司の質問に即答できず、沈黙が訪れることでさらに緊張感が高まる可能性もあります。そのような状態では、自らの自己評価を正しく伝えることは難しいため、事前の準備が重要となります。
自己評価を行う際に意識したいポイントは以下です。
・目標に対する成果や達成度
・スキルのアピール
・仕事に対する意欲や姿勢
事前に振り返りを行い、伝えたいことやアピールしたいことをまとめておくことで、緊張感のある評価面談でも自分の思いを伝えられるでしょう。
できたこと・できなかったことを客観視できる
自己評価のヒアリングは、「自らを客観的に分析できるか」をチェックする目的を持ちます。
自分を客観的に分析できる社員スタッフには、以下の共通点があります。
・業務上でのトラブルに冷静に対処ができる
・ハングリー精神があり、勉強を怠らない
・社内外でも良好な人間関係を築ける
どれも業務遂行やキャリア形成において、重要なことです。評価面談を通じて、社員スタッフの長所を改めて再発見するケースも少なくありません。
そして、業績と行動結果の裏付けに、「偶然ではなく、客観的な視点があったため」だと初めて気が付き、評価を上げるのも珍しくありません。
改善案を提出する
残念ながら評価期間中の実績と行動評価がイマイチな場合もあります。その際、評価面談では、特に以下に注目します。
・失敗から何を学んだか
・問題本質を見抜き、解決へ導く力があるか
・何に努力すべきか、考える努力をしているか
評価期間中の結果に対する姿勢から、以下のような印象を受けます。
・トライ&エラーを恐れない気持ち
・仕事に対するモチベーションの高さ
・仕事への責任感、計画性がある
今期の評価期間において、実質的な評価アップはできないものの、来期の評価時に「評価が上がる対象」と考えられます。
一例として、「100%完璧な改善案ができてから上司へチェックをあおぐ」ことを心掛けた社員スタッフがいました。100%の改善案を求めた結果、その改善案は主観的で、穴が多い粗末なものでした。その社員スタッフは、ほかの要因もあり「評価が下がる」という結果に…。
評価者は完璧な改善案を求めていません。例えそれが、100%完成された改善案ではなく、60%でも構いません。大事なのは、60%の完成度でも早く考案し、上司や周りの社員スタッフとの連携を通して、改善案をブラッシュアップすることだったのです。この手順のほうが、はるかに、スピーディーで完成度の高い改善案ができ、評価が上がります。
目標が明確化
今期の評価結果に対して、「目標を明確に意識して出た結果」もしくは「目標意識は薄く、偶然に出た結果」なのか、どちらが普段から高い目標意識で取り組んでいるかは、明白です。評価期間中は、仕事への目標意識として以下を評価します。
・適切な情報を社内に共有をしているか
・目標達成に、合理的な判断ができているか
評価をする際「目標が明確化された結果なのか」をチェックします。
・評価期間中に与えられた目標数字
・目標数字に対する結果(達成率)
これらの項目は、最低限聞いている内容です。どんな職種であっても、仕事結果は「数字」で表せます。常に明確な目標意識を持ち、業務に取り組んでいるならば、当然答えられるはず。
今期に加え、来期の目標を自分の中で明確化し、目標意識を強く持つ社員スタッフは「評価が上がる」対象となります。
【被評価者向け】評価面談で評価が下がる人
逆に「評価面談を通じて評価が下がる人」の行動や振る舞いにも特徴があります。こちらも実体験をもとに紹介します。
評価結果に対して消極的
評価面談をする際、「評価は既に決定されているから、しょうがない」と、評価に対して「いわれるがまま」の社員スタッフも存在します。
評価面談の目的には、「社員スタッフ・企業との目線合わせ」があります。消極的な状態では思考が停止し、自分の成長を止めてしまうでしょう。
過去の事例では、「はい、はい」とひたすら話を聞く社員スタッフがいました。これでは、「評価」を伝えるだけで、社員スタッフの潜在的な能力を引き出す面談にはならず、社員スタッフにとっても、今後のキャリアにおける大きな機会損失につながります。
・どうして自分はこの「評価」なのか
・課題へのアプローチは他にないだろうか
など、評価面談を受ける社員スタッフには、考えるべきタスクが山積みです。自分の評価に対する疑問やハングリー精神を持つと、よい評価面談ができるでしょう。
冷静に話せない
評価面談は、客観的事実に基づき公正な評価をすることが大前提です。しかし、一方的で主観的に話す社員スタッフもいます。
「私が○○を頑張ったから、この結果を出せた。自分の功績だ。」と主張する被評価者もいます。もちろん、被評価者が主張する「頑張り」は事実です。しかし、業務実績は、自分一人だけの功績ではありません。
例えば、
・見積書や契約書の作成
・お客様への資料作り
・経費申請処理
・オフィスの備品調達
・関係部署への根回し
・上司の確認
など、全て周りの協力があってこそ達成できた功績なのです。
評価面談は、自分の功績をアピールする場所ではなく、公正な評価と今後の成長促進が目的です。「自分が! 自分が!」という、一方的で強い主観を持つ社員スタッフに、マイナスな評価は避けられません。
当事者意識がない
当事者意識がない社員スタッフは、仕事に対する本気度も低く、切れ味がある実績は残せません。
ここでいう、「当事者意識」とは
・社会人としての責任感
・「自分が結果を出す」という強い意志
・適切に報連相を行い、業務遂行を進める熱意
・模範となる社会人を目指すこと
を意味しています。
しかし、この「当事者意識」を「会社へ心身ともに捧げなさい」という意味だと捉える社員スタッフもいます。正しくは、「法令を遵守した労働環境の中、いかに効率よく結果を出す意識があるか」というものです。
企業に属する以上、当事者意識を持ち、常に会社と個人の成長追求する社員スタッフが評価されるのは、至極当然です。
【被評価者向け】評価面談前にできる評価エラー対策
ごくまれに、評価エラーが発生します。
・適切な情報共有ミス
・被評価者のコミュニケーション能力不足
・評価者の実力不足
要因はさまざまありますが、これらが主なきっかけとなります。公正な評価をするために、被評価者は以下の点に注意しましょう。
業務内容を書き出す
評価面談時には、限られた時間内で端的に面談を行う必要があります。効率的で、かつ端的な時間を持って、クオリティが高い面談をしなければなりません。
自分の業務内容をより明確に被評価者と共有すると、スムーズで余裕を持った評価面談が可能になるでしょう。
具体的に、自分が担当している業務内容を書き出しましょう。
・どんな業務に
・どれほどの時間を
・どこの部署と連携して
・いくらの費用が必要なのか
最低限、この4項目を評価者や上司と共有してください。
緊張してうまく話すのが難しい、または、頭の中で整理不足だと感じる社員スタッフも、極まれにいます。整理不足や緊張のために、評価エラーが起きるのは、今後のキャリアにおいても大きな機会損失です。
あらかじめ自分の業務整理をすれば、余裕が生まれ、リラックスして面談に臨めるでしょう。また、事前に冷静に見直すことで、効率化につながる業務改善案の発見にもつながります。
業務結果の事実を書き出す
自分が担当した業務結果の事実を書き出してください。客観的な事実を、冷静に受け止めることが重要です。
実績結果によって、過剰な「驕り・へりくだり」など、評価面談に必要ない感情が先行します。
評価はあくまで、実績と行動に対しての評価です。以下の業務結果の事実を明確にしましょう。
・目標との達成率
・今までに達成できたか
・時間・コストはどれほどか
少なくとも、上記3つは書き出しておきます。
上記事実の客観的根拠があれば、詳しい問題解決までのアプローチ方法や今後の改善点などが明確に分かり、面談に深みが出ます。
希望するキャリアを伝える
自分が希望するキャリアを考えましょう。
・1年の短期
・2年~5年の中長期
というように、短期から中長期のスパンを見て、より詳細に書き出してください。
評価面談の結果では、「今後のキャリア形成として、○○分野に取り組んでもらいたい」と、上長や各部署に連絡があることもあります。
評価面談では、現状の業務結果をもとに「業務内容は適性か?」という判断も行われます。もしあなたが「希望しない部署・職種にいる状況」なら、ミスマッチが生じ、十分な能力も発揮しにくいかもしれません。
自分が希望するキャリア・挑戦したい職種があれば必ず、理由も一緒に伝えておきましょう。
まとめ
評価面談は、評価者・被評価者の双方にとって、今後の成長に関わる貴重な機会です。評価者は評価面談を通じ、メンバーの育成とマネジメントの見直しを行います。被評価者は、自分の客観的な評価を知り、今後のキャリアを考えるきっかけにします。
評価者・被評価者ともに心して臨み、実りある面談にしましょう。